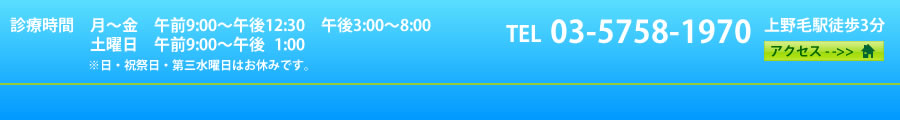



戦国時代の武道の書物には「殺法」「活法」の記述が見られ、「殺法」とは武技そのもので、「活法」は傷ついた者の治療法や手当てで、骨折・脱臼・捻挫・打撲などの怪我や、出血・仮死者に対する蘇生法なども含まれています。
この「殺法」と「活法」は、文武の道として表裏一体となって進歩発展し、「殺法」は健康増進や精神修行の手段として、または、例えば柔道のように競技や運動として現在行われています。一方「活法」は医療の一部として、接骨院で行われる柔道整復術へと発展してきました。つまり、接骨院が行う施術というのは、日本古来からの柔術・武術のもう一つの面である「人を活かす」ことを目的として施されるものなのです。
現在では効果的な物理療法や電気療法なども行われていますが、折れてずれてしまった骨や外れてしまった関節を元の位置に戻したり、症状に合わせて様々な材料を使い患部を固定する所などに、独特のやり方を見ることができます。
電気を身体にかける際の強さは、心地良い強さが基本です。強ければ強いほど効果が上がるわけではありませんのでご注意ください。我慢するほど強いと、筋肉の緊張度が高まってしまい、かえって逆効果になる場合もあります。弱くても電気を感じていれば効果はあります。ただし、弱すぎると物足りなく感じると思いますので、自分が心地良いと思うところで声をかけて下さいね。
目安として、電気をかけながらも寝ることができるぐらいが良いと思います。治療の途中でも「強くて痛いなぁ」「物足りないなぁ」など感じましたら、遠慮なく声をかけて下さいね。
湿布には皆さんご存知のように、冷湿布と温湿布があります。が・・・実はほとんどの皆さんは誤解されています。冷湿布といっても冷やしているわけではありません。温湿布といっても温めているわけではありません。あくまでも「そのように感じさせている」だけなのです。湿布は消炎鎮痛剤です。つまり、炎症を抑えて、痛みを鎮めるものなのです。ですから、「冷やす」「温める」といった効果はありません。当院では温湿布はお勧めいたしません。温湿布はトウガラシのエキスを入れて、ピリピリ・ジンジン感じさせているからです。肌の敏感な方は、すぐにかぶれてしまいます。
湿布の効果は4〜5時間です。4〜5時間経ったら剥がしてください。4〜5時間経たなくても、あまりにピリピリしたり、かゆくなったりしたら剥がしてください。1日に貼る回数は、その人のケガや痛みの状態にもよりますが、1〜3回でよいです。ただし、はがした後は、すぐに次の湿布を貼るのではなく、しばらく(2〜3時間)肌を休ませてから貼るようにしましょう。
患部を冷やすには、氷水が一番効果があります。生理的に0度が一番良いのです。保冷剤や氷でも良いのですが、冷たすぎるので濡れタオルに巻くなどの工夫をしましょう。
通常、ギクッとさせてしまったときは(捻った・ぶつけた・伸ばした等のケガはすべて)、冷やすのが良いです。特に脈が打つように「ズキンズキン」していたり、痛めたところが熱を持ち「熱く感じる」場合は必ず冷やすようにしましょう。最初の痛みを「10」としたら「5」以下、つまり半分以下に痛みが治まってきたら温めるようにします。あくまで目安ですが、痛めてから3〜5日は冷やして、その後は徐々に温めるのが良いでしょう。
まったく動くことができないほど症状が強く出ている「ぎっくり腰」は、無理をして病院や接骨院に足を運ぶ必要はありません。数日は家で冷やして、痛みがある程度治まってきたら受診するようにしましょう。
鼻緒のある履き物は、5本指すべてが鍛えられ、転びそうになっても安定性が増すといいます。足の裏全体がバランスよく鍛えられ、足の筋肉をバランスよく使えるようになり、親指と中指の間で挟んで履くことによって、親指を正しい方向に向けるので外反母趾になりにくく、通気性がいいので水虫予防にもなるといわれています。
最近、外反母指について問題視されていますが、デザイン性の高い靴をはかないという訳にもいかない女性の方はもちろん、男性の方、小さい子供さんにまで見られるようです。足にもっと適度な良い刺激を与えてあげてほしいのです。足に負担をかけたぶん、家に帰ったら休息と指の補整をして下さい。会社の中でも事務職の方などは、靴を脱いで足を楽にしてあげて下さいね。